離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

婚姻生活に色々な問題が発生し、夫婦関係が悪化すれば、離婚を考え始めるのが通常の流れです。
その際、夫婦の間に子供がいないのであれば、基本的には二人の問題ですし、自分のことだけを考えれば済みます。
一方、子供がいるのであれば、離婚が子供に与える影響は多大なるものとなります。
そのことを考慮せずに、離婚を安易に決断すれば、子供の人生を大きく狂わすことにもなりかねません。
今回は、「離婚が子供にどのような影響を与えるのか」をテーマとして取り上げます。
また、離婚を選択した際の子供に及ぶ悪影響を極力抑える為に、何をすべきか?等についてもお伝えします。
子供をお持ちの方で、現在離婚を考えている方は、離婚に責任が無い子供を犠牲にしない為にも、是非ご覧ください。

離婚が子供に及ぼす影響について、家族問題の第一人者である、ジュディス・ ウォラースタイン氏は次のように述べています。
離婚が原因で、子供は自身の成長に絶対不可欠な「家庭の構造」を失うからである。
家庭は子供が幼少期から多感な時期への、成長のステップを移る上での重要となる。
家庭は 子供の心とからだの精神の発達を助けてくれるのである。
この構造が崩れると 子供の世界は一時的にかなめを失ってしまう。
そして子供は孤独を感じ、現在と未来に強い不安を抱くのだ。
大人の父母は離婚することで、新しい人生を送れる・やり直しが可能であると思うでしょう。
しかし、その離婚のメリットの考え方は全て自分中心です。
子供はその引き換えに、上記のような健全な人格形成に不可欠&かけがえのないものを失うことになります。
家庭の構造が崩壊するとは、つまり父と母、両者からの親子関係断裂が発生することです。
どういうことかといえば、
離婚すると多くのケースでは、父親は子供から離れて暮らすことになります。(親子関係断絶その1)
そして母親は、何とか家計を支えようと仕事に必死となり、子供の世話やコミュニケーションが疎かになります。(親子関係断絶その2)
この様な親子関係断絶した環境で、子供が育つ結果として、子供は後に数々の不幸に襲われることに繋がるのです。

ウォラースタイン氏が、離婚が子供に与える問題を発表する以前は、離婚は子供に何ら影響がないと考えられていました。
しかし、離婚が子供に影響することに関して、ウォラースタイン氏をはじめ、各国で調査が実践され、実際に悪影響があることが確認されました。
主には以下の4つのことについて影響がありました。
ウォラースタイン氏は、両親が離婚した子供を長期間にわたって追跡調査したところ、子供達は深刻な精神的ダメージを受けていることを確認しました。
子供達は、両方の親から見捨てられるかもという不安を持たせ、そのことにより勉強に集中が出来ません。
加えて、一緒に暮らす親も外での労働時間が多くなり、子供に気を配れなくなります。
それにより、学業成績が悪く、成人後の社会的地位も低い傾向が見られます。
バージニア大学のヘザーリントン教授の研究によると、両親が離婚した子供は、精神的トラブルを抱える可能性が高いと発表しています。
具体的には、両親がそろっている子供のうち、精神的に問題が無い子供の割合は90%である。
治療を必要とするような精神的なトラブルを持つ子供は10%である。
それに対して、両親が離婚した子供では、それぞれ75%と25%である。
アメリカのある調査機関が行った調査結果によると、離婚により父親(母親)のいない少女の妊娠は、両親が揃っている家庭で育つ少女が妊娠する確率の2.5倍である。
一人親家庭では、子供の行動や友人関係に注意の行き届かないことが多いです。
子供は両親から得ることができない安心感や情愛を得ようと、異性に強い興味を持ちます。
その結果、不純異性交遊に走る傾向が高くなるのです。
昨今の日本の研究によると、これまで紹介した事例の他に次の様な悪影響があることが確認されています。
ひきこもりや登校拒否、深刻な抑うつ状態などの非社会的な不適応行為。
金品持ち出し、無断外泊、未成年での喫煙、アルコール依存症、果てにはドラッグの依存症になる等、反社会的な行為などに陥る可能性が高くなることも指摘されています。

両親が離婚した子供は、その子供自身が将来離婚をする確率、または未婚の母親になる確率が高くなっています。
確率的には、両親が揃った環境で育った子供の約3倍になるという調査結果が出ています。
もちろん両親の離婚とその子供の離婚との間に、法的な関連性は一切ありません。
とは言うものの、親の家庭環境、行動スタイルが子供に影響を与える可能性はあります。
あえて言うなら、このことが連鎖のではないかと思います。
その結果、将来自身の婚姻相手においても、無意識のうちに同じ行動を取る恐れがあります。
離婚後においては、母子家庭(父子家庭)が原因で経済状況が苦しくなり、大学あるいは高校への進学を断念。
その為、収入の低い職に就くほかなく、貧困状況が連鎖し、婚姻後も経済状況が苦しくなる状況が繰り返される、という様なケースもあります。
シングルマザー等は子供を育てるために必至で働かなければならず、子供にとって親の愛情等を要する時期に子供とコミュニケーションが取れる時間が限定されてしまいます。
当然ながら、子供にはまだ家庭事情が全て理解できません。
よって「自分は愛されなかった」と心の葛藤や悲しさ等を抱えてしまい、愛情飢餓だったり、精神的に不安定な状態となるのです。
そのことで、その子供の人格性形成などに、次のような悪影響が出てします。
このような理由で、夫婦関係にトラブルが起きた時に修復するのが難しいのかもしれません。
自身の両親が離婚していることで、離婚というイメージがしやすいです。
加えて、実際にそのような環境で育った為「親も離婚しているから」「親も未婚だから」とどこか諦めてしまう節があります。
この様なことが要因となり、離婚に対してのハードルが下がりやすい傾向があります。

ここまで離婚が子供に及ぼす影響についてお伝えしました。
離婚が子供に及ぼす影響を考えれば、離婚をしないことに越したことはありません。
とはいえ、夫婦の状況によっては離婚した方が望ましいケースもあります。
特にDV(極度のモラハラも含む)は、その行為を受けている側は心身ともに危険が及ぶ為に離婚すべきでしょう。
また両親の一方が子供を虐待している場合も同様です。
その様な家庭環境で子供が育つことで、その子供の心に大きな闇を抱え込ませてしまい、その闇がこの先ずっと苦しめることになります。
子供が取り返しのつかない様な事態にならない為にも、離婚は仕方ないと言えます。
DVやモラハラ、虐待などの事情がなければ、子供のことを考えれば離婚はするべきではありません。
だからといって、子供が大きくなるまで仮面夫婦の状態を続ければいい、という訳では決してありません。
子供の為だと思い、離婚せずに仮面夫婦を演じることは、むしろ逆効果になることがほとんどです。
仮面夫婦は、周囲には仲の良い夫婦を偽っているため、表面上一般的な夫婦同じ様に見えます。
しかし、家庭内ではそうはいきません。
そのような状況下の家庭で育った、子供への悪影響は大きいです。
なかには「子供だから分からないだろう」という考えを持っている方もいるでしょう。
しかし、どれだけ幼くても子供は、その異様な雰囲気をすぐに次のように感じ取ります。
「僕が良い子にしておかないとパパとママが仲良くならない・・・」
などと、自分を責めたり、親の顔色を常に伺う、または常に自分の感情を押し殺し、我慢するようになります。
また険悪すぎる両親を見ることに堪えかねず、心の中でうまく消化できないことで、SOS的な意思を含めていると思われる、次のような行動を取る子供もいます。
この状態が更にひどくなれば鬱病や摂食障害などの精神にも支障をきたすようになります。
以上の事から、子供の為に仮面夫婦を続けていくというのは、むしろ子供を苦しめる事となり、大きな問題があるといえます。

夫婦関係は冷え切っているし、仮面夫婦を演じることがダメならば、もはや離婚しかない・・・と思うかもしれません。
でも、そう考える前に夫婦関係の修復を一度試みてから、離婚するか否かの判断を私はすべきだと考えます。
実際に夫婦関係の修復を試みたことで、離婚を回避でき、夫婦の絆を取り戻せたという例はたくさんあります。
離婚をする方の多くは、冷え切った夫婦関係の修復を試みることなく終わってしまっているのです。
子供の為であることはもちろん、自分自身の為にも離婚を回避し、夫婦関係を修復させ、良好な時の関係に戻れるなら、それが一番です。
よって、離婚を決断する前に夫婦関係の修復を試みることをお勧めします。
恥ずかしながら、ここまで子供が離婚に及ぼす影響等についてお伝えしておきながら、当時の私自身は子供のことを考えていませんでした。
正確に言えば、自分のことで一杯になり、考えられなかった。
でも後になり、やはり離婚を早まったことを少し後悔しています。
経済的な面から我慢させていること、たまに仕事で帰る時間が遅い日が続き、寂しい思いをさせていることはもちろん。
というのは、息子が父親と会った時に、嬉しそうに何があったのかを私に細かく伝えるのです。
それを見た時、「この子から父親を遠ざけてしまった。あの時にもう少し我慢して夫との話し合いを持つ機会を持つべきだった」
夫婦関係の修復を早々に諦めた自分を責めました。
これをご覧頂いている方は、私と同じような思いをして頂きたくはありません。
ですので、夫婦修復の余地があるのであれば、子供の為にも、そして自分の為にも夫婦修復を模索して頂ければと思います。
冷え切った夫婦関係を修復するには、相手次第だと考えがちですが、そんなことはありません。
相手の態度はさほど関係ありません。
「相手を変えようとするのではなく、まずは自分自身が変わる」 ことが何より重要なのです。
私がこれまで見てきた夫婦関係を修復できた方の多くは、実際にこの考えを基に動かれていました。
自身は何もすることなく、ただ静かにジッとしていたって、相手の心はもちろん動かない。
ですので、何よりも自分自身が変わらないといけません。
自身が変われば、相手も変えることが可能です。
※ 夫婦関係の修復についての詳細は「これが、夫婦関係を修復させる方法となります」で取り上げています。

夫婦関係の修復を試みたが駄目だったという方は、残念ですが離婚する方向になります。
離婚するには、夫婦で養育費や財産分与などの離婚条件を話し合う必要があります。
※ 離婚条件についての話し合い等の詳細は「適切な離婚の進め方がその後の生活の安定へ!進め方の6つの掟はこれ」で取り上げています。
その離婚協議中においては、より一層の子供への配慮が必要となります。
離婚を進めている最中は、父親も母親も子供をそっちのけで自分たちの問題を優先します。
そのことで、しつけ、遊び、身のまわりの世話、フォローなどあらゆる面で親が子にすべきことが減少します。
明らかに子供のことは二の次でコミュニケーション不足となり、子供の要求に鈍感となります。
この時期、両親は自分たちが望んでいることは、そのまま子供の望みと勘違いしがちとなります。
一方の子供は、親以上に、不安や恐れを抱いていますが、親を困らせたくない、悲しませたくないと考えています。
よって離婚協議中は、本心を吐き出せる環境では全然ない為、当然に子供は遠慮をしやすくなります。
「僕さえ、私さえ、ガマンしておけば」と思うのです。
また離婚について話し合っている夫婦の間には、基本的に信頼関係はほとんどありません。
そんな二人が離婚条件などについて話し合う為、非常に感情的になりやすく、ときには夫婦でなじりあい、攻撃し合うのです。
離婚協議がこじれて、時間が掛れば掛かるほど、子供は家族が崩壊するのをまの当たりにします。
そして、その事態をどうすることも出来ない無力な自分を責めるのです。
自己嫌悪に陥ったその子供は、健やかに日々を送るために欠かせない「自己承認力・自己肯定感」さえ奪い取ります。
お伝えした通り、親は自分たちのことで精一杯ですので、そんな子供の心の声を感じ取ることができません。
よって、子供が抱えているこの深刻な症状について、見落とすことになってしまうのです。
子供への配慮が欠けることにより、子供は極めて深刻な心の苦しみを負いますから、人格形成への多大な悪影響は免れません。
ですので、その様な事態とならない様に、離婚協議中は気にしすぎるくらいに、子供に対しての配慮が求められます。
たとえば、離婚の話し合いは子供の前ではしない、いつも以上に子供とのコミュニケーションを取るといったことです。
もし、子供をそっちのけで離婚協議を進めていたのなら、今すぐに安心を与える為に、お子さんを抱きしめてあげてください
そして、これまで悲しく辛い思いをさせたことを謝ることで、お子さんは救われますから。

ここからは、子供に離婚の事実を伝える際の注意点についてお伝えします。
父母が離婚することを聞かされたとき、子供は大きくショックを受けます。
このことは避けられません。
ですので、子供が受けるショックを最小限に抑える為にも、離婚の事実の伝え方は適切でなければなりません。
伝え方のポイントは次の4つです。
別れる配偶者の悪口は避け、離婚の事実だけ伝えてください。
たとえば次のような悪口はNGです。
などと、相手配偶者の悪口を言い、自分だけ正当化し続けると、子供が大きくなった時、逆に不信感を抱かれ、親子関係がおかしくなってしまう恐れがあります。
また、子供は両親から血を引いている。
よって自分も父のような「悪い人間」になってしまう等、自信喪失等に繋がる恐れがあります。
子供が幼いから分からないだろうと思い、次の様に誤魔化そうとしてはいけません。
「パパは仕事で遠い国に行くことなり、もう帰ってこない」
このような誤魔化しをすると、あとで本当のことが分かった時、親に強い不信感を持ちます。
そのことで人間不信になったり、非行に走ったりする可能性があります。
子供には離婚の事実を、その子の年齢に合わせてきちんと説明し、父母も残念と感じていると伝えることです。
また子どもは「離婚となったのは僕が悪い子だったからだ・・・」
このように捉えて、罪悪感に苦しんでしまうこともあります。
ですので、離婚する原因が子供ではないことをハッキリと伝え、理解してもらうことが重要です。
離婚しても両親から愛されていると子供に感じてもらう為には、面会交流は何よりも重要です。
ですので「ママとパパはもう一緒に暮らせないけど、パパはあなたの父であることはずっと変わらないよ」
「これからもパパと会ってお話ししたり、遊ぶことができるからね」などと、伝えてください。

私は離婚前に別居していたのですが、息子が次のようなことを聞いてきました。
「いつパパに会えるの?」
「パパに会えなくて寂しい」
この言葉を聞いたときに強いショックを受けました。
「どうして!?」「夫に父親の資格はないのに」という感情が出てきました。
しかし、それは私が夫に不倫されたことから出てくるもの、だと気づきました。
「私の事情はこの子には関係ない・・・この子は父親を必要としている」
このように感じ、それまでは消極的だった面会交流を設けようと考えました。
子供を引き取る側の多くは、この面会交流の設定を嫌がるのをよく見受けられます。
また面会交流を拒否する理由としては、「子供が父親に会いたくないと言っている」という方が多いです。
しかし子供の本心は、そこには無いのです。
離婚協議中はお互いが言い争うことが多く、感情的になる為「あんなお父さんとは会いたくないでしょ?」と子供に聞いてしまう。
子供は幼いほど母親のことを強く求めています。
絶対的な存在です。
そんな存在である母親に嫌われて見捨てられてしまえば、生きていけない、という危機感を本能的に感じてしまう。
だから本音では父親と会いたくても、母親に見捨てられてしまう、という考えから、会わなくてもいいと答えるのです。
こうやって無理やり親子の関係性を絶たれることで、子供は「父親から見捨てられてしまった」と深く傷つきます。
そして「僕(私)が駄目な子だからパパは会ってくれない」「僕が悪い」等と自己否定に走ってしまうのです。
このような思いをさせることで、その子の健全な人格形成を大きく阻害させてしまいます。
それを防ぐためには、離れて暮らす父親との面会交流をなるべく多く実施し、「僕は父親から愛されている」と子供が実感すること。
ですので、父親が子供に暴力を振るう等の問題なければ、自分の感情や都合は捨て、積極的な面会交流を設定することです。
それが、離婚が子供に与える影響を最小限に抑えることに繋がりますから。
※ 面会交流の詳細は「面会交流のルール作りをする上で必ず押さえておきたいポイント」をご覧ください
今回は「離婚が子供にどの様な影響を与えるのか」をテーマとして取り上げました。
離婚は親の勝手な都合によるもので、子供には何の責任もありません。
ですので親の離婚で、子供がしわ寄せを受けることなどあってはならないのです。
子供の事を考えれば、DVなどの特別な事情がない限り、夫婦関係の修復を目指し、離婚を回避させるのが一番です。
夫婦関係修復を試みたが、どうしても溝が埋められず離婚となれば、子供への最大限の配慮を心掛け、離婚を進めてください。
それでは最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
離婚を考えるほど悪くなった夫婦関係を変えるには、相手次第だと思いがちですが、実際はそうではありません。
あなた自身の行動次第で夫や妻の考えを変えることができます。
そのことについて詳しく取り上げています。
夫婦関係の修復の仕方で悩んでいる方は下のボタンよりご覧ください。↓
スポンサーリンク

妻に浮気を許してもらうには?適切な行動を解説【償い・反省・誠意】



旦那の浮気を許すことを考え中なら失敗しない為に知っておくべき事



夫の浮気から夫婦再構築させる為に押さえるべき4つのポイント



旦那が嫌いで離婚したい!それを成功させる為の全手順をお教えします



【妻から離婚したいと言われたら】理想の結末を迎えるための6つのポイント
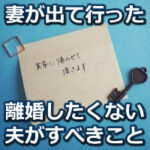
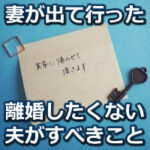
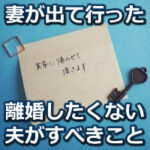
【妻が出て行った】離婚したくない方が別居中にすべきことを徹底解説



妻からの離婚請求を回避し、夫婦関係を修復させる為の確かな方法



未払い養育費を請求して全額回収!元夫の逃げ得を防ぐ手段を解説



養育費を継続的かつ確実に払わせる方法を徹底解説!



離婚のメリットとデメリットを徹底解説!間違いのない決断を導く