離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

こんにちは、まいみらいです。
離婚の話し合いのなかで、揉めれば特に深刻になるのが、子供の親権をどちらが持つかについてです。
もし話し合いで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に場を移して親権を争うことになります。
そうなったときに「自分は親権者になれるのだろうか?」と不安になりますよね。
そこで今回は、親権についての詳細と共に、家庭裁判所が親権者として求めるものを主に取り上げます。
親権だけは譲れないとお考えの方は、必ず知っておくべき内容をお伝えしています。
スポンサーリンク

親権とは、未成年者の子供を保護、養育し、子供の財産を管理する親の権利・義務です。
この親権を行使する者のことを「親権者」と言います。
婚姻中は共同親権といい、父母ともに親権があります。
しかし離婚をする場合には、共同親権は認められていません。
一方の親を親権者とする必要があり、それが決まっていないと、離婚届は受理されません。
なお子供が20歳以上である場合や、または20歳になっていなくても結婚している場合は、親権者を決める必要はありません。
ところで、親権は「親の権利」のように思われがちですが、本来保護を要する子供の為にあるものと考えられています。
どちらが親権者になるかで揉めている。
長引きそうな為、まずは離婚を先に成立させたい。
そこで、とりあえずどちらかを仮の親権者にして離婚届を提出。
その後、改めてじっくり話し合いをしよう、という考え方は持つべきではありません。
自分たちが仮の親権者のつもりでも、提出した離婚届に記載したとおりに戸籍に記入されてしまいます。
一度戸籍に記載されてしまうと、親権者を変更するには、必ず家庭裁判所の許可が必要となるのです。
そして一度親権者を定めて協議離婚してしまった以上、親権者の変更は、よほどのことが無い限り認められません。
ですので、この様な軽率な親権者の決め方をするのは、絶対に避けなければなりません。
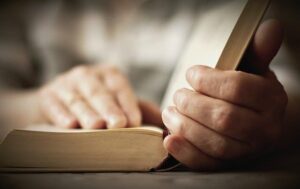
親権の内容は法律的に「身上監護権」と「財産管理権」の二つに大別されます。
身上監護権とは何かを大まかに言うと、子供の身上を保護することの権利・義務のこと。
同じく財産管理権とは、子供の財産を保護する権利・義務をのことです。
それでは個別の具体的内容を見ていきます。
身上監護権の具体的内容は次の通りです。
財産管理権の具体的内容は次の通りです。
※1 補足説明
契約の同意・取消権、法定代理権など、子供が法律行為をする必要がある時に、子供に代わって法律行為を行うことです。

協議離婚をするに際して、夫婦に未成年の子供がいる場合は、話合いによって夫婦のどちらかを親権者に決定します。
その際は、親の都合だけで考えるのではなく、「子供の負担を最小限にするにはどうすべきか?」
「子供にとって幸せとは何か?」という観点から考えることです。
離婚の話し合いのなかでも、揉めると特に深刻になるのが親権者選び。
子供にとっては、両親が離婚することだけでも大きなショックを受けています。
その上、親権争いが勃発することで、子供の心はさらに深く傷つきます。
子供の精神的影響を考えると、話合いで円満に決めるのが理想です。
それが難しい場合は、子供の目の前の話し合いは避ける、話し声が聞こえないようになどの最低限の配慮をするべきです。
なお、離婚が子供に与える影響について詳細は「離婚が子供に与える影響【子供の心理に着目】必ずご確認ください」で取り上げています。
話し合いの際には、親権者のほかに、監護者を決めることもできます。
つまり親権者になれなくても、監護権者となれば子供の世話や身の回りのことができます。
ただし子供の財産の管理はできません。
親権者と監護者を分ける場合のケース例は次の通り。
父親が親権者になることを主張し、母親もそのことを認めている。
しかし父親が仕事で忙しく、通常の養育が十分に出来ない。
よって母親が監護権者として子供を引き取り、共に生活するというスタイルです。
ただし親権者と監護権者を分けることは、離婚後も親同士が一定の信頼関係を築けることが絶対条件です。
なぜなら、子供が日常生活するにおいては、別々の役割を持つ親権者と監護権やの協力を必要としなければならない時があります。
親権者と監護権者が協力できないのであれば、子供の日常生活に支障をきたすことになります。
具体例を出すと、子供が交通事故でケガを負い、その損害賠償を求める裁判をしたいと思っても、親権者の同意がとれないと提起できません。
他には、監護者である母親が離婚を機に旧姓に戻した場合、一緒に生活する子供の苗字は、母親と同じにしたいところです。
この場合も親権者の同意がとれないと、それが出来ません。
離婚時に、子供と一緒に生活できる監護権さえあればいいと思ったが、この様な不都合が実際に生じて後悔する方は少なくありません。
よって、離婚後に親同士が一定の協力関係を築けない恐れが少しでもあるのなら、親権者と監護権者は分けるべきではないと考えます。
※監護者についての詳細は「親権を分けて監護権者の設定を考えている方が知っておくべきこと」で取り上げています。
子供の出産前に離婚する場合は、戸籍に子供の記載がありませんので、離婚届に親権者を記載する必要はありません。
そして離婚後に生まれてきた子供は、当然に母親が親権者になることになっています。
出生後に父親を親権者と定めることも可能ではありますが、乳児ですから困難です。
裁判所は子供の年齢が低ければ低いほど、親権者は母親がふさわしいと考えているからです。

話し合いで親権者が決まらない場合には、家庭裁判所へ「離婚調停の申し立て」を行い、調停により親権者を決定することになります。
離婚調停とは、当事者夫婦と中立的な第三者である調停委員を交え、親権者について話し合いをし、合意を目指す場です。
調停委員とは夫婦の言い分を聞き、その上でアドバイスや解決案を出し、お互いが合意できるように導く役割を担っています。
離婚調停でも合意形成が出来ない場合は、家庭裁判所の審判によって親権者を指定されることになります。
審判とは、調停が不成立の際にこれまでの事情を踏まえ、裁判所自らの判断で親権者を決定することです。
これを「審判決定」といい、判決と同様の効果があります。
ただし、この審判決定に対しては2週間以内に、当事者から異議申し立てをすることが可能です。
異議申し立てがあると即座に審判の効力が失われます。
申立人:夫または妻
申立先:原則、相手方の住所地の家庭裁判所
必要書類:申立書、戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)
申立費用:収入印紙1,200円、予納郵便切手
※離婚調停の流れ等の詳細は「協議離婚ができない場合の次のステップ離婚調停を分かり易く解説」で取り上げています。

離婚調停・審判でも親権者が決まらない場合は、離婚裁判を提起し、父母のどちらを親権者とするのかを決めます。
その際の判断基準は、父母のどちらが親権者となるのが子供は幸せであるか?というになります。
具体的な内容は後ほどお伝えします。
原告:夫または妻
被告:配偶者
申立先:原則、原告または被告のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類:訴状2部、戸籍謄本、源泉徴収票、預貯金通帳などの証拠とする書類のコピー
訴訟費用:収入印紙、予納郵便切手
※訴訟で何を決め、何を訴えるか等で必要書類や訴訟費用は変わってきます。
裁判所の場では、自身の親権者の適格性を主張していきますが、裁判所によってはその陳述書の雛形が用意されている所もあります。
東京家庭裁判所にあることは確認できています。(その書類のダウンロードページはこちらから)
陳述書の主な内容としては、自身の生活状況、子供の状況、監護補助者の存在、監護計画、その他こどもの監護に関すること、です。
これらの内容に沿って記載し、自身の優位性、及び相手の不適格性を主張してきます。
スポンサーリンク

次に家庭裁判所が、親権者を決める際の判断基準となる要素についてお伝えします。
審判などで家庭裁判所が親権者を決める際に重視するのは「子供の利益」と「福祉」にかなうかどうかです。
つまり子供が成長する上で、どちらの親が親権者として適格性があるか?ということです。
親権争いの際、「俺の方が経済力は高いのだから、親権者に指定される。だから親権を争っても無駄だぞ!」
この様なやりとりがよくありますが、正しい理解ではありません。
経済力は親権者を決定する上での、1つの考慮事項に過ぎないからです。
お互いの経済力の差は、一方が義務である養育費を支払うことで解決できる為、経済力だけが全てではありません。
「子供の利益」と「福祉」とは具体的には次の様な内容となります。
それでは個別の具体的内容を見ていきます。
次のような事情が比較されます。
また父母が育児に専念できずに、監護補助者を必要とする場合は補助者自身の心身状況、育児経験の有無なども考慮されます。
父母自身に子供を育てる意思・意欲はあるかどうか、子供に対する愛情はあるのかどうかを比較します。
当然ですが子供に対する愛情が大きい方が、より親権者として適切だと判断されます。
家庭裁判所が特に重要視する1つが、子供自身の年齢や意思となります。
それでは年齢別に取り上げています。
10歳未満の子供は、父親より母親の愛情を強く必要としています。
ですので一般的には母親の元で監護されること、母親とのスキンシップによる養育が一番幸せだと考えられています。
その為、母親が親権者に指定される傾向が強いといえます。
10歳以上15歳未満の場合も10歳未満の子供と同様、母親が親権者に指定されるケースが多いです。
但し、子供の意思が考慮される場合もあります
15歳以上になると、必ず家庭裁判所が子供の意思を確認して、その内容を尊重して親権者を決めることになっています。
裁判所は子供の意思に拘束される訳ではありませんが、その意思を大いに重要視しています。
家庭裁判所が特に重要視する1つです。
急激な生活環境の変化をもたらすような親権者・監護者の決定の仕方は、子供の心理的負担をかけるとされています。
その為、現状に暮らしている親を親権者に指定する傾向があります。
例えば、親権者争いの対象である子供の年齢が10歳未満で、その子供は別居中の父親の元で長年暮らしているとします。
10歳未満の子供なので、通常なら家庭裁判所は母親を親権者として指定するところ、
子供が日々の生活に慣れている父親側の環境で、暮らすことが一番と考えて父親を親権者として指定します。
この様な傾向を「現状維持の原則」といいます。
※ 現状維持の原則の詳細は「連れ去り別居された子供を取り戻す!適切な方法を解説【親権確保】」で取り上げています。
家庭裁判所は親権者を指定する際、兄の親権者は父、妹の親権は母というようには分けず、どちらか一方を親権者に指定します。
これを「兄弟姉妹の不分離」の原則といいます。
兄弟姉妹が一緒に暮らすことは、かけがえのない事であり、子供の福祉や利益に適うからです。
しかし、次の様な例外的なケースもあります。
離婚前の別居で長い間、兄弟姉妹が父親と母親それぞれ別々に育てられ、子供が別居後の生活に順応している。
この場合、安定した状態を変化させるのは、逆に子供に負担を与えるとして、兄弟姉妹は別々の親権者が指定される傾向があります。
以上が親権者になれる人の要素となります。

親権を家庭裁判所の審判などで争った場合、どうしても父親は不利な状況におかれます。
繰り返しになりますが、特に10歳未満の子供については、どうしても母親が必要と考えられている為、父親を親権者とするのは稀です。
ただし、夫婦が別居中で子供が父親と共に暮らしている場合や、15歳以上の子供が父親と暮らしたい、
という意思表示をしている場合には、父親にも親権が得られることも大いにあります。
他には母親のネグレクトが酷い場合や、子供にいつも暴力を振うなど、母親に問題がある場合も同様です。
この様な事情がなければ、自身が親権者に選ばれるように最善を尽くす他ありませんが、現実はやはり母親が指定される事が大半です。
であれば、父親側とすれば親権を諦める代わりに、子供との面会交流の回数を増やすことを提案することが一番ベターです。
母親側も親権を諦めてくれるなら、その点は認めてくれることが十分考えられます。
※父親の親権者指定について詳細は「父親が親権者を得る為の5つの要素」で取り上げています。(私の別のブログに移動します。)

子供の親権は譲る代わりに、養育費を払わないという考え方や主張をする父親(母親)は多いです。
しかし親は子供に対し「生活保持の義務」があります。
生活保持義務とは、お互いに同程度の生活レベルを確保する扶養義務のことです。
親権者・監護者になるかならないか、離婚後の面会交流を認めるか否かなどに関係なく、養育費は親として当然に分担する必要があります。
加えて、子供と一緒に暮らしていないという事情は、子供と一緒に生活している親よりも、扶養の義務が軽くなるものではありません。
裁判所も養育費と親権者の関連性について以下の通りに判断しています。(福岡高決昭52・12・20より)
両親は親権の有無に関係なく、それぞれの親の資力に応じて未成熟子の養育費を負担する義務を負うものである。
よって、親権者となった親側が第一次的に扶養義務を負担すべきであると解することはできない。
※父親が養育費の支払いを拒否してきた時の対処法等の詳細は「「養育費は払わない!」と言ってきた場合の対処法をお教えします」で取り上げています。

最後に両親の一方に次の様な事情などがある状態で、親権を争った場合の基本的な考え方をお伝えします。
それでは個別に見ていきます。
夫婦の一方が不倫したことを理由に、親権者としてふさわしくないという主張がよくされることがあります。
しかし不倫をしたからといって、必ずしも親権者になれないという訳でありません。
不倫をした有責性はあまり重要視すべきではなく、子供の親権者として、ふさわしいか否かが何より重要だからです。
もちろん不倫をしたことに加え、子供の面倒を全く見ないような事情があれば別です。
しかし不倫をしたことと、子供の親権者として適格性を欠くということは、必ずしもリンクするものではありません。
親権を争っている専業主婦のよくある不安として、今、無職でも親権を取れるのだろうか?というものがあります。
結論からお伝えすると、現在無職だとしても親権を取ることは可能です。
お伝えした通り、親権を決める際に重要するのは「子供の福祉」です。
すなわち、「子供にとってどちらの方が親権者となるのが幸せなのか」ということなのです。
確かに、親権を望む一方の親が継続的な収入があること、経済的に豊かであることも「子供の福祉」を考える要素のひとつです。
しかし「子供の福祉」は経済力の豊かさだけでは決まりません。
「精神的に満たされるか」がとても重要な要素となります。
だからこそ10歳未満の子供は本能的に母親を求めるので、大方は母親が親権者に指定されているのです。
相手配偶者に犯罪行為があり刑罰が与えられた場合、犯罪者である相手を親権者として指定される様なことがあるのか?についてです。
子供の健全な育成にとって、どちらがよりふさわしいかという観点から考えた時、その犯罪歴が影響しないという判断もあり得ますん。
当然、現在の生活状況が悪く、再犯の恐れがある等といった事情ならば、親権者として不適格であると判断がされるでしょう。
今回は親権についての詳細と共に、家庭裁判所が親権者として求めるものを主に取り上げました。
これから親権者をどちらにするかを話し合う方や、実際に今どちらがなるのかで揉めている方などの参考になれば幸いです。
最後に繰り返しになりますが、子供にとっては両親が離婚することだけでも大きなショックを受けています。
ですので、間違っても子供の前で親権争いをしてはいけません。
親権の話し合いの際は、子供に対しての出来る限りの配慮を忘れないことです。
それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きましてありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
あなたは弁護士を通して、離婚や財産分与、慰謝料請求を考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?
このような希望を満たしてくれる弁護士等を「無料」で探してもらえる案内所があります。
理想かつ離婚に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンからご覧ください。↓
スポンサーリンク

旦那の浮気を許すことを考え中なら失敗しない為に知っておくべき事



夫の浮気から夫婦再構築させる為に押さえるべき4つのポイント



旦那が嫌いで離婚したい!それを成功させる為の全手順をお教えします



妻からの離婚請求を回避し、夫婦関係を修復させる為の確かな方法



未払い養育費を請求して全額回収!元夫の逃げ得を防ぐ手段を解説



養育費を継続的かつ確実に払わせる方法を徹底解説!



離婚のメリットとデメリットを徹底解説!間違いのない決断を導く



離婚の適切なタイミングをCHECK!【失敗しない為の6つのポイント】



離婚の迷いをスッキリ解決!正しい決断をする為に押さえるべき掟



離婚を後悔しない!その為の適切な手順を詳しくお教えします