離婚を専門に扱う某法務事務所に勤める1児のシングルマザーが、離婚に関する役立つ知識を発信します。

こんにちは、まいみらいです。
離婚の年金分割の制度がスタートしてから、10年以上が経過しました。
この制度が様々なメディアで取り上げられた為、一般の方にもある程度は浸透していますが、正しく理解をしている方は少ないです。
実際に私も「離婚の年金分割の手続きをすれば、夫の年金の半分が貰える」と誤った認識を当初していました。
私のような勘違いをしている方は結構おられます。
でも、そんな簡単な仕組みではなく、単純に年金が半分受け取れるという認識では離婚後になって、
「こんなはずではなかったのに・・・」と強く後悔することになりかねません。
そこで今回は、離婚の年金分割を正しく理解して頂く為に、日本の年金制度や年金分割の詳細、手続き方法などについて詳しく取り上げます。
スポンサーリンク
最初に、そもそも離婚の年金分割とは何か?についてお伝えします。
平成19年3月以前の離婚では、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫の国民年金を除く厚生年金の全額が夫に支払われていました。
妻が受け取れる年金は国民年金だけとなり、入ってくる年金は満額支給で約80万円と少額です。
熟年離婚の場合、妻は新しい職をみつけることが困難であり、これでは経済的に不安定な状況になってしまいます。
そもそも夫(妻)が支払ってきた年金の保険料は、婚姻生活を通じて、夫婦双方で協力して支払ってきたものです。
そこで夫婦間の公平をはかる為、年金を共有財産と考え、財産分与の対象とする年金分割の制度が平成19年4月以降に始まりました。
具体的には、老後に支給される値金額の基礎となる標準報酬額について、婚姻期間中の支払額を多い方から少ない方へ移動させます。
標準報酬額とは、簡単にいえば支払保険料のことです。
年金分割の対象は主に夫の年金だけだと思われがちですが、そうではありません。
夫婦が共働きで、妻が勤め先の社会保険に加入している場合は、妻の標準報酬額も対象となります。
ですので、もし妻の方が掛けている年金が多いならば、妻の年金の一部が夫へ分与されることになります。
離婚の年金分割を理解する上で、現在の日本の年金制度を知っておく必要がありますので簡単に取り上げますね。
公的年金はすべての国民に加入が義務付けられています。
職業に応じて次のいずれかの制度に加入することになります。
年金制度はよく3階建ての建物に例えられます。
それでは個別に見ていきます。
「国民年金」は3階建ての土台となる1階部分にあたり、自営業者や学生などが加入しています。
国民年金の保険料は一律で、月額16,410円(令和元年度現在)となっています。
「厚生年金」は3階建ての2階部分にあたるもので、会社員などが加入しています。
厚生年金の加入者は同時に国民年金に加入することになります。
「共済年金」は厚生年金と同じく3階建ての2階部分にあたるもので、地方公務員、私立学校の教職員の人が加入しています。
共済年金の加入者も同時に国民年金に加入となっています。
3階部分に当たるのは、会社では国民年金基金、厚生年金基金、企業年金です。
なお、共済年金では職域加算部分となります。
国民年金は加入者の職業によって3種類に分けられております。
⇒国民年金加入者
■第2号被保険者
⇒厚生年金や共済年金の加入者
■第3号被保険者
⇒会社員や公務員に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人
冒頭でもふれた通り、離婚すると夫の年金の半分がもらえると考えておられる方は多いようですが、残念ながらそうではありません。
まず離婚の年金分割の対象になるのは、「2階部分」である、厚生年金と共済年金部分のみです。
1階部分の国民年金や、3階部分の企業年金などは、対象外なので年金分割できません。
ですので、夫(妻)が自営業なら、厚生年金や共済年金に加入することできない為、離婚の年金分割制度を利用できません。
補足ですが、確かに企業年金は年金分割の対象ではありませんが、双方が合意できるなら、財産分与の対象とすることは可能です。
そして年金分割の対象となる期間ですが、夫(妻)が厚生年金、若しくは共済年金に加入したすべての期間ではありません。
年金分割対象となるのは、「婚姻期間」に対応する部分だけとなります。
夫(妻)が婚姻前、離婚後に支払った保険料については、対象外なので注意が必要です。
たとえば、夫の厚生年金加入期間が40年、婚姻期間が30年とします。
夫が年金に40年加入していても、30年の婚姻期間の部分しか対象になりませんので、40年÷30年=「4分の3」が期間となります。
つまり、年金分割の対象となるのは、厚生年金(共済年金)の「4分の3」の部分だけということになります。
余談ですが、私も離婚時に年金分割をしましたが、結婚年数が7年しかなかったので、年金分割による年金は少額だろうと思います。
とはいえ、たとえ数百円程度となっても、継続的に受け取れるならありがたいです。

ここまで年金制度や、年金分割の対象となる部分について取り上げてきました。
それでは次に年金分割の種類についてお伝えします。
年金分割は次の2つの制度が分かれます。
どちらの制度も、離婚により年金が分割されるという制度ですが、それぞれの趣旨や仕組みが異なっています。
それでは、それぞれの制度について詳しく取り上げてきます。
合意分割とは離婚時、夫婦どちらかの請求によって、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割できる制度です。
年金を分割するかどうか、また分割割合はどうするのかは、夫婦間で合意または裁判所の決定によります。
合意分割の按分割合は最大で「2分の1」となっています。
3号分割とは、第3号被保険者である妻(夫)からの請求により、夫(妻)の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割できる制度です。
この3号分割制度の特徴は、夫の同意は必要なく、妻から分割請求だけで年金が分割できる点です。
ですので、夫がどれだけ年金分割をしたくないと拒否しても、3号分割の請求さえすれば問題なくできます。
しかし、分割できる保険納付記録は平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、妻が第3号被保険者であった期間だけです。
ちなみに、ほぼ専業主婦だった私も、3号分割制度を利用して年金分割をしました。
婚姻期間が平成15年4月から平成30年2月までとします。
年金分割請求者は専業主婦である妻です。
この場合、合意分割も3号分割も同時に請求できるの?
という様な疑問が出てくると思いますが、同時請求はできます。
この場合「合意分割」を請求すれば、同時に「3号分割」も請求したとみなされます。
つまり平成20年度4月から平成30年2月までの期間分について、必ず2分の1の割合で分割した額が受け取れます。
その上さらに「合意分割」によって、平成20年3月以前の期間分について、2分の1を上限として年金分割も可能となります。
合意分割の制度を利用する場合には、まずは夫婦の話し合いで按分の割合を決めていきます。
その話し合いにおいて、どのような流れで進めればいいかをお伝えします。
年金分割の按分割合を決める際には、夫婦それぞれの年金についての情報が分からないと決められません。
そこで夫婦の具体的な年金の情報を知る為に、年金事務所に行きましょう。
そして「年金分割のための情報提供請求書」を提出し「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。
妻に厚生年金の期間がある場合は夫婦両方の分を取得が必要です。
この請求は離婚前にでき、また請求者の配偶者には請求があったことを秘密にしてくれます。
年金分割のための情報通知書を入手するには年金分割のための情報提供請求書ともに添付書類として次の書類が必要です。
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
事実婚関係にあった期間があれば、事実婚関係を明らかにする書類があれば請求できます。
情報提供された年金分割のための情報通知書を見れば、按分割合の上限と下限が記載されています。
年金分割のための情報通知書を入手すれば、それをもとに夫婦で年金分割の按分割合について話し合います。
先ほども書いたとおり、合意分割の分割割合は最大で「2分の1」となっています。
年金分割を請求する側とすれば、一体どれくらいの按分割合が相場なのかが、非常に気なりますよね。
結論からお伝えすると、過去の裁判例のほとんどが「2分の1」とされています。
具体的には厚生労働省が公表している統計「厚生年金保険・国民年金事業年報」の平成29年度版を見てみると、
10%~20%未満・・・0.1%
20%~30%未満・・・0.2%
30%~40%未満・・・0.8%
40%~50%未満・・・1.5%
5 0% ・・・97.4%
これは裁判外の取り決めも含めての数値ですが、50%以下の取り決めが稀なくらいです。
また「0%~10%未満」はゼロですので、相手が年金分割を拒否しても、裁判で求めれば必ず年金分割を受けることができるといえます。
夫婦が長期別居しているという事情は、年金分割の按分割合に影響を及ぼすものでしょうか。
結論からお伝えすると、ほぼ影響はなく、家庭裁判所の判断はやはり「2分の1」がほとんどです。
家庭裁判所の考えは、年金分割は「特別な事情がない限り、互いに同等にみるのを原則」としています。
その特別な事情に「長期間の別居」は当てはまりにくいのが現状です。
過去の判例で、「7年間」の別居期間でも、特別な事情と判断することはできない旨を判断がされています。(札幌高裁平成19.6.26)
話し合いで分割割合がまとまらない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停にて分割割合を定めることとなります。
調停とは、当事者である夫婦と中立的な第三者である調停委員を交えて、分割割合について話し、合意を目指す場です。
調停委員とは夫婦の言い分を聞き、その上でアドバイスや解決案を出し、お互いが合意できるように導く役割を担っています。
年金分割の調停の申し立ての手続きを行うには、次の書類を用意する必要があります。
調停申立書などの書類の提出先は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」が基本です。
申し立てにかかる費用は収入印紙1200円と連絡用の郵便切手(約800円)となります。
なお、離婚がまだ成立していない場合には、「離婚調停」の付随申し立てとして、同調停の中で按分割合を定めます。
離婚が成立している場合は、請求すべき按分割合を定める「年金分割調停」を新たに申し立てます。
年金分割が調停によっても合意できない場合は、当事者の一方の申し立てにより家庭裁判所に「審判」を求めることができます。
審判とは、家庭裁判所がこれまでの当事者の一切の事情を考慮して、按分割合を決定することです。
なお審判は調停前置主義がとられていますので、離婚調停を経ずに最初から審判を求めることはできません。
年金分割の審判の申し立て手続きを行うには、次の書類を用意する必要があります。
審判申立書などの書類の提出先は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」が基本です。
申し立てにかかる費用は収入印紙1,350円分(1200円分と150円分)と連絡用の郵便切手が必要となります。
なお、年金分割の為の情報提供請求書は、年金事務所で配布されてますし、年金基金のホームページからも入手可能です。
調停や審判によっても按分割合について合意ができない場合、最終的には訴訟を起こし、家庭裁判所に判断してもらいます。
ただし、訴訟には莫大な費用と時間がかかりますので、なるべく調停や審判で合意することが望ましいのは言うまでもありません。
夫婦の合意または調停などにより年金分割の按分割合が決めると、つぎに厚生労働大臣に対して標準報酬の改定請求をします。
改定請求の手続きは、夫婦の話し合いで決まったのか、それとも裁判手続き(調停・審判など)によって決まったのかで手続きが変わってきます。
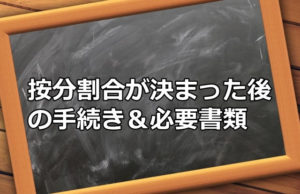
まずは夫婦の話し合いにより、按分割合を決めた場合の手続きの流れなどをお伝えします。
基本的には元夫婦で一緒に年金事務所に行き、「年金分割の改定請求」を行います。
必要書類は次の通りです。(日本年金機構の公表PDFから引用)
①標準報酬改定請求書
②請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
③婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書またはそれぞれの戸籍の個人事項証明書のいずれかの書類)
④請求日前1カ月以内に作成された、お二人に生存を証明できる書類(戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書、それぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類)
⑤事実婚関係にある期間の合意分割を請求する場合は、その事実を明らかにできる書類(住民票等)
⑥年金分割を明らかにできる次の書類
・話し合いにより、年金分割の割合をさだめたときに、年金分割することおよび按分割合について合意している旨を記入し、みずから署名した書類(様式は年金事務所に備えてあります)
⑦年金分割の請求をされる方(代理人を含む)の本人確認ができる書類(運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、印鑑およびその印鑑にかかる印鑑踏力証明書のいずれかの書類
この改定請求の手続きは、離婚後にしかできません。
標準報酬額改定請求書のフォーマットは、年金事務所で配布されていますし、年金事務所や年金機構のホームページからも入手可能。
必要書類は、「コピー可」と記載されているもの以外は、原本で提出する必要があります。
合意分割の対象期間に、3号分割の対象となる期間が含まれているときは、合意分割を請求した時点で3号分割の請求があったとみなします。
また元夫婦が一緒に顔を合わすのが嫌だという方もいるでしょう。
その場合は代理人に依頼し、代わりに一緒に行ってもらうことも可能ですが、専用の委任状が必要です。
次のの書類を用意すれば、一人だけでも手続きをすることも可能です。
按分割合の話し合いがまとまったが、離婚後に相手が非協力的になるケースもあります。
相手の気持ちが変わる前に公正証書等を作成しておくほうが安心です。
※公正証書の詳細は「離婚協議書を公正証書にすることで効力は絶大となります」で取り上げています。
元夫婦のどちらか一方が年金事務所に行き、「年金分割の改定請求」を行います
必要書類は先ほどお伝えした①~⑦の書類ですが、⑥の「年金分割を明らかにできる次の書類」が次の書類にいずれかに変わります。
3号分割の請求だけの手続きは、第三号被保険者が次の書類を用意して、離婚後に年金事務所にて請求すれば手続き完了です。
相手と一緒に年金事務所に出向く必要はなく1人でできます。。
②請求者の年金手帳
③婚姻期間等を明らかにできる書類※
④請求日前1ヵ月以内に作成された、“相手方”の生存を証明できる書類(戸籍抄本、戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類)
※の書類の具体的な内容は分割請求の場合と同じです。
繰り返しになりますが、3号分割請求だけを請求する場合は、夫婦の合意の必要はありません。
年金分割制度では、先ほどお伝えした請求の手続きを行わないと、分割された年金を受け取ることができません。
そして請求には期限があります。
請求期限は原則として、合意分割、3号分割ともに離婚成立の日から2年以内に手続をする必要があります。
年金事務所の窓口は事務的な対応しかしませんので、たった1日でも請求手続きが遅れれば権利を失う可能性が高いです。
ちなみに私は、離婚後の色々な手続きや就職活動で手一杯になり、この年金分割の手続きをすっかり忘れていました。
バタバタが落ち着いた3ヶ月後くらいに、この手続きを忘れていることに気づき、あわてて請求し事無きを得ました。
私のように、途中で気づけばいいのですが、ずっと忘れたまま2年が経過し、年金分割ができなくなった方も珍しくありません。
ですので、この手続きを忘れない為にも、離婚後なるべく早めにすべきです。
離婚してから2年間が過ぎる前に、家庭裁判所に年金分割の調停や審判の申し立てを行い、それをやっている間に2年が過ぎた。
または請求の期限経過日前1ヵ月以内に按分割合を決める調停の成立、審判の確定をした場合などは、
成立(確定)した日の翌日から起算して「1カ月以内」に分割請求の手続きをする必要があります。
1カ月間しかないので、訴求に手続きをしないと間に合わないことに注意が必要です。
分割した年金の受け取りは、相手の年金支給が開始された時ではなく、自分の年金を受給できるようになった時からです。
年金分割した後であれば、元夫が再婚したり、先に死亡しても、1度確定した年金分割の権利には影響ありません。
また分割された年金を受け取るには、自身の最低限の受給要件である25年以上の年金を納めることが絶対です。
そうでないと、分割分はもちろん、ご自身の年金も受取れませんので・・・
今回は年金分割についての全体像を取り上げました。
制度が複雑なので分かりにくいとは思いますが、ご覧頂いたことで年金分割のイメージ、手続き方法などがお分かり頂けたと思います。
年金分割をされる方の参考になれば幸いです。
それでは長くなりましたが、最後までご覧頂きありがとうございました。
まいみらいがお伝えしました。(私の離婚経緯などを載せたプロフィールはこちら)
関連記事
財産分与は夫婦に共有財産があれば、必ず分与を確保できる権利なのでしっかりした対策を。
あなたは弁護士を通して、離婚や財産分与、年金分割の請求を考えているが、次のような悩みや考えをお持ちではないでしょうか?
このような希望を満たしてくれる弁護士等を「無料」で探してもらえる案内所があります。
理想かつ離婚に強い弁護士をお探しの方は、詳細を下のオレンジ色のボタンからご覧ください。↓
スポンサーリンク

旦那の浮気を許すことを考え中なら失敗しない為に知っておくべき事



夫の浮気から夫婦再構築させる為に押さえるべき4つのポイント



旦那が嫌いで離婚したい!それを成功させる為の全手順をお教えします



妻からの離婚請求を回避し、夫婦関係を修復させる為の確かな方法



未払い養育費を請求して全額回収!元夫の逃げ得を防ぐ手段を解説



養育費を継続的かつ確実に払わせる方法を徹底解説!



離婚のメリットとデメリットを徹底解説!間違いのない決断を導く



離婚の適切なタイミングをCHECK!【失敗しない為の6つのポイント】



離婚の迷いをスッキリ解決!正しい決断をする為に押さえるべき掟



離婚を後悔しない!その為の適切な手順を詳しくお教えします